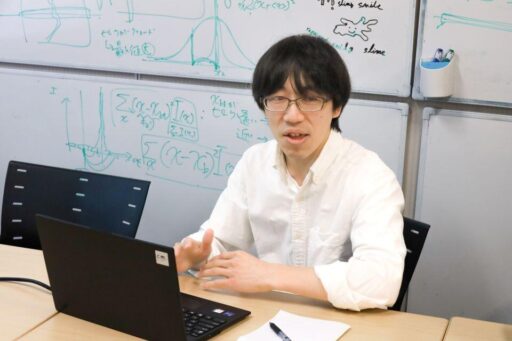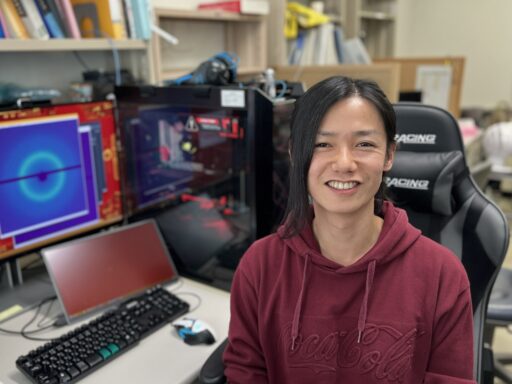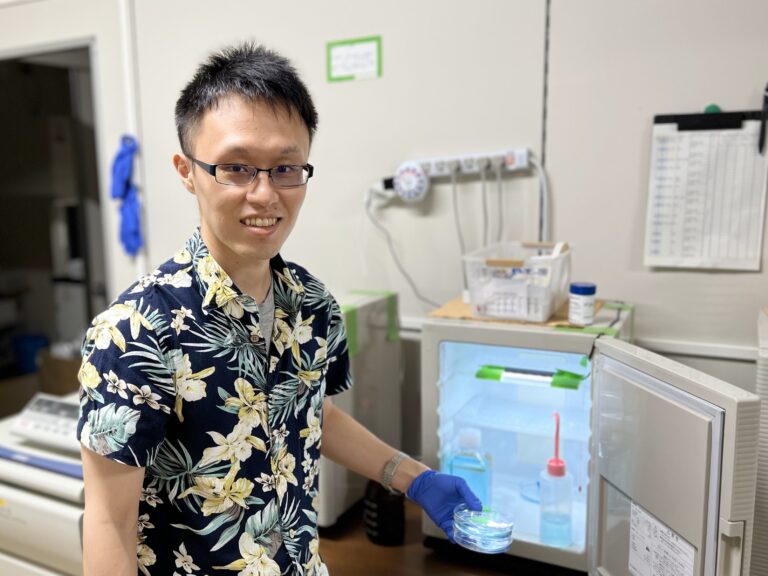
私たちは両親から遺伝情報を1対ずつ引き継いでいます。どちらか片方の情報しかないと、生きられないのだそうです。特に魚類などが生きられない理由は、100年以上前から謎のままでした。
この長年の謎に迫る研究をしたのが、齋藤 大輝(さいとう だいき)さん(生命科学院 生命融合科学コース 博士後期課程1年)です。プレスリリース「ゼブラフィッシュ半数体症候群の細胞異常を特定」(2024年10月21日)について、齋藤さんにインタビューしました。
半数体って何ですか?
生物が生きるために必要な遺伝情報全体のことを、ゲノムといいます。ヒトは母方と父方から1セットずつ全ゲノムを引き継ぐので、計2セットの全ゲノムを持ち、この状態を二倍体と言います。対照的に、片方から1セットのみのゲノム引き継いだ状態を半数体と言います。全ゲノム情報を1セット分は持っているにも関わらず、脊椎動物は半数体の状態では生きられません。半数体がなぜ育たないのか、その仕組みを研究しています。
どのように研究するのですか?
ゼブラフィッシュを使って実験しています。遺伝情報が引き継がれないように処理した精子を、正常な未授精卵に受精させ、半数体の受精卵を作ります。その後、育った胚(はい)の状態のままで大きさや組織の形を観察したり、固定処理(生存時の分子の並びを維持しながら標本にする処理)をしてから細胞の中の器官や分子を蛍光で標識して配置や数を調べたりもしました。

何が分かりましたか?
半数体では死んでしまう細胞が増えました。細胞がストレスを受けることで、細胞自体を死なせるようなタンパク質が増えるからです。また細胞分裂も遅くなります。染色体というDNAの塊を細胞内で子孫細胞に均等に分配することを役割の一つとして持つ中心体という細胞内小器官が減少してしまい、分裂が途中で止まってしまうことが原因と考えられます。つまり、半数体が十分に成長できないのは、細胞が死んでしまうことと、細胞分裂が遅れることが原因の一端だと分かりました。

苦労したことは?
弊研究室で主流の実験方法は培養細胞を用いたものであり、そのノウハウを魚の細胞実験に活用することが難しかったです。
例えば、胚や仔魚は厚みがあるため、細胞の画像から得られる蛍光の量や器官の明瞭さなどは、場所によってばらつきが生じることが避けられません。一方、培養細胞は平たい皿の上に並んで2次元状に飼われているため、ばらつきが生じにくいという違いがあります。
弊研究室で使用されている自動で画像を解析するツール類は、後者の培養細胞向けのものがほとんどです。そのため、魚の実験では使用できず、手動で解析することになったのが作業量的に大変でした。
🐟
また、厳密さの程度に対する疑念にも悩まされたため、生物の個体を専門としている研究者から解析方法や結果の解釈等についてアドバイスをもらうこともありました。
🐟
別の例としては、弊研究室のヒト細胞の実験で使用されている試薬が、魚に有効であるかについても未知数なものが多く、さらに有効性の検証にも時間がかかるため苦労しました。特に、リビジョンという「期限までに審査員の提示する実験をして、その結果次第で論文への掲載の可否が決まる過程」の中で、時間に追われる中で新しい試薬を試した時は中々の修羅場でした(笑)。
今回の結果は、どのようなことにつながりますか?
半数体は、遺伝子工学や品種改良に役立つ可能性があります。半数体が育たない原因を解明して、さらに大人まで成長させられるような解決方法を開発できれば、更なる活用の道の模索にもつながると考えています。
つまり、半数体が正常に成長させることができてからが、新たな活用方法の探索のスタートになるとも言えます。
最後に、これから研究を始める学生に向けて、メッセージをどうぞ!
このプロジェクトに限らず基礎的な研究で得られた知見を活かせるかどうかは、これからの科学に携わる我々の手にかかっており、その活用方法も我々の自由です。
今これを読んでいる画面の前の皆さんにもその一翼を担うチャンスが広がっています。
これを読んで深く知りたくなった方、自分ならこう使ってみたいというアイディアを持った方は、是非細胞装置学研究室まで。我々は歓迎いたします。※事前のアポイントメントはお忘れなく。