1年次で生命科学の最先端に触れる
「科学・技術の世界」、「一般教育演習」

1年次全学教育科目の教養科目・主題別科目区分で、1学期「科学・技術の世界 (はじめての生命科学)」、2学期「科学・技術の世界 (生命科学の最前線)」が開講されます。また、2020年度から新たに全学教育科目1学期「一般教育演習(持続可能な開発目標(SDGs)と生命科学)」も開講しています。
これらは、理学部生物科学科(高分子機能学専修分野)の教員が担当します。
数々の生命の現象や実験をオムニバス形式で講義します。テーマディスカッションやクリッカー・クイズなどアクティブラーニングによる学生との対話授業を進めます。生命を「知る・支える・模倣する」科学の観点から学び、社会・環境・経済・AIとの”意外なつながり”を認識する機会として、多くの学生に受講してほしいと願っています。
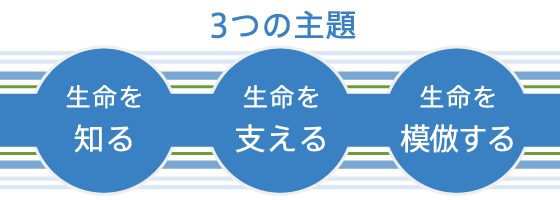
2026年度 全学教育科目 講義予定一覧
タイトルをクリックすると講義内容詳細に飛びます。
講義日程が変更になる場合もあります。
第1学期 月曜5限 開講予定
「科学・技術の世界(はじめての生命科学)」
| 4月13日 | 黒川 孝幸 | 1. | ガイダンス |
| 4月20日 | 芳賀 永 | 2. | がん細胞の動きを止めろ︕ |
| 4月27日 | 第2回講義担当者 | 3. | ディスカッション① |
| 5月11日 | 相沢 智康 | 4. | つくって役立つタンパク質 |
| 5月18日 | 第4回講義担当者 | 5. | ディスカッション② |
| 5月25日 | 中村 公則 | 6. | 共生する腸内細菌と私たちの健康 |
| 6月1日 | 第6回講義担当者 | 7. | ディスカッション③ |
| 6月8日 | 中岡 慎治 | 8. | 数学を通して理解する生命現象 |
| 6月15日 | 第8回講義担当者 | 9. | ディスカッション④ |
| 6月22日 | 李 响 | 10. | 生命のナノ構造 |
| 6月29日 | 第10回講義担当者 | 11. | ディスカッション⑤ |
| 7月6日 | 居城 邦治 | 12. | なぜ分子は自然に集まるのか? |
| 7月13日 | 第12回講義担当者 | 13. | ディスカッション⑥ |
| 7月27日 | 黒川 孝幸 | 14. | 生き物の匠をまねる |
| 8月3日 | 第14回講義担当者 | 15. | ディスカッション⑦ |
第2学期 月曜5限 開講予定
「科学・技術の世界(生命科学の最前線)」
| 10月5日 | 比能 洋 | 1. | ガイダンス |
| 10月15日(木) | 野々山 貴行 | 2. | 自然が選んだ剛と柔の融合 |
| 10月19日 | 石原 誠一郎 | 3. | ふかふかベッドで健やかな細胞 |
| 10月26日 | 新井 達也 | 4. | 凍結と戦う生命 |
| 11月2日 | 第2, 3, 4回講義担当者 | 5. | 最前線訪問① |
| 11月9日 | 菊川 峰志 | 6. | 光生物学への招待 |
| 11月16日 | 横井 友樹 | 7. | 腸から考える免疫のしくみ |
| 11月30日 | 山口 諒 | 8. | 進化を予測する |
| 12月7日 | 第6, 7, 8回講義担当者 | 9. | 最前線訪問② |
| 12月14日 | 安井 知己 | 10. | やわらかくて、強くて、運べる ― ゲルの基礎と設計指針 |
| 12月21日 | 安田 傑 | 11. | 生命を形作る高分子の科学 |
| 1月4日 | 安達 広明 | 12. | 植物免疫研究〜大発見のその時〜 |
| 1月13日(水) | 第10, 11, 12回講義担当者 | 13. | 最前線訪問③ |
| 1月18日 | 比能 洋 | 14. | 糖と生命 |
| 1月25日 | 第14回講義担当者 | 15. | 総合ディスカッション |
講義内容詳細 第1学期
1. ガイダンス、質問受付、授業概要説明
大学1年生(文系・理系)が初めて学ぶ科学・技術の世界の中で、「生命科学」分野の授業です。初回は履修ガイダンス。授業担当の学科について紹介を行います。また、授業の進め方(学生参加のクリッカー利用練習、ディスカッションの方法など)、成績評価レポートについて説明します。
キーワード : ガイダンス
2. がん細胞の動きを止めろ︕
がんは日本人の死因の第1位であり、いまや2人に1人ががんになるといわれています。がんが進行すると、がん細胞は動く能力を獲得して体中のあちこちに移動し、新たな腫瘍を形成します。この現象は浸潤、転移とよばれ、がんで亡くなる患者の8~9割を占めます。したがって、がん細胞の動きを止めることが治療の大きな課題となっています。本講義では、がん細胞が動くメカニズムとそれを止めるための最新の技術について学びます。
キーワード : がん、細胞運動、浸潤・転移
3. ディスカッション①
第2回講義担当者
1学期開講の講義中 第2回の講義を総括し、総合討論を行います。これまで学んできた講義において、生命科学が様々な学問分野の融合であることを理解し、視野を広げられたことで、将来どのような科学・技術に応用可能であるかを教員と学生、学生と学生で確認、討論します。
キーワード : 生命科学、グループ討論、発表
4. つくって役立つタンパク質
タンパク質は様々な生命現象において重要な役割を担っていますが、その解析を進め、医療や産業への応用を目指す際には、機能を持ったタンパク質をどのように「上手につくる」のかが重要な鍵となります。これはタンパク質がどのように正しい立体構造を形成して機能を持つのかとも関連する問題です。本講義では、タンパク質を「上手につくる」技術が、研究や産業においてどのように応用されているのかについて学びます。
キーワード : タンパク質、遺伝子組換え、構造生物、産業利用
5. ディスカッション②
第4回講義担当者
1学期開講の講義中 第4回の講義を総括し、総合討論を行います。これまで学んできた講義において、生命科学が様々な学問分野の融合であることを理解し、視野を広げられたことで、将来どのような科学・技術に応用可能であるかを教員と学生、学生と学生で確認、討論します。
キーワード : 生命科学、グループ討論、発表
6. 共生する腸内細菌と私たちの健康
40兆を超える細菌が私たちの腸内には共生しており、これらは腸内細菌叢を形成することで免疫や代謝などのさまざまな生体機能を制御しています。この腸内細菌叢のバランス破綻は、肥満や糖尿病などの生活習慣病、さらにはうつ病や自閉症などの発症に関与することが知られてきています。本講義では、腸内細菌が、私たちの健康や病気に及ぼす影響を紹介します。
キーワード : 腸内細菌、粘膜免疫、健康、病気
7. ディスカッション③
第6回講義担当者
1学期開講の講義中 第6回の講義を総括し、総合討論を行います。これまで学んできた講義において、生命科学が様々な学問分野の融合であることを理解し、視野を広げられたことで、将来どのような科学・技術に応用可能であるかを教員と学生、学生と学生で確認、討論します。
キーワード : 生命科学、グループ討論、発表
8. 数学を通して理解する生命現象
計測や通信情報技術が発達したことで、動物の動きや気候といった生物の環境の状態を把握できるようになった。ミクロの世界では、遺伝子発現の状態を網羅的に計測できるようになり、生命活動の一端を表すデータや知見が得られるようになっている。この講義では、様々な生命現象に関するデータの解析手法、数理モデルと呼ばれる刻々と時間変化する状態を記述する数学手法、コンピューターによるシミュレーションなど、生命現象を理解するための数学について紹介します。
キーワード : 数理生物学、数理モデリング、データサイエンス
9. ディスカッション④
第8回講義担当者
1学期開講の講義中 第8回の講義を総括し、総合討論を行います。これまで学んできた講義において、生命科学が様々な学問分野の融合であることを理解し、視野を広げられたことで、将来どのような科学・技術に応用可能であるかを教員と学生、学生と学生で確認、討論します。
キーワード : 生命科学、グループ討論、発表
10. 生命のナノ構造
生き物は丸みのある形を取っていますが、ナノレベルで見ると、実は無数の紐(高分子)からできています。これらの紐が高次構造を形成し、さらに複合体を形成することで、複雑に制御された機能を発現しています。本講義では、光・X線・中性子などの量子ビーム散乱を用いてナノ構造を観測する方法をご紹介します。ぜひ一緒に、逆空間の世界でのナノ構造や分子運動を見てみましょう。
キーワード : 高分子、ナノ構造、逆空間
11. ディスカッション⑤
第10回講義担当者
1学期開講の講義中 第10回の講義を総括し、総合討論を行います。これまで学んできた講義において、生命科学が様々な学問分野の融合であることを理解し、視野を広げられたことで、将来どのような科学・技術に応用可能であるかを教員と学生、学生と学生で確認、討論します。
キーワード : 生命科学、グループ討論、発表
12. なぜ分子は自然に集まるのか?
細胞の中では様々な分子が相互作用しています。例えば、細胞膜は脂質分子が向きを揃えて整列・会合した二分子膜からできています。酵素は基質となる分子の特定の位置と結合して、基質を合成・分解します。DNAは相補的な水素結合で結ばれた塩基対によって二重らせん構造を形成します。多数のアミノ酸が連なるポリペプチドはおりたたまれて3次元構造を作ります。このように生体では分子は自然と集まり働いているように見えます。なぜ、分子は自然に集まるのでしょうか?本講義では、物理化学の観点からその理由を考えるともに、それらを模倣した分子系バイオミメティクスについて紹介します。
キーワード : 自己組織化、自己集合、超分子化学、ホスト―ゲスト化学、物理化学
13. ディスカッション⑥
第12回講義担当者
1学期開講の講義中 第12回の講義を総括し、総合討論を行います。これまで学んできた講義において、生命科学が様々な学問分野の融合であることを理解し、視野を広げられたことで、将来どのような科学・技術に応用可能であるかを教員と学生、学生と学生で確認、討論します。
キーワード : 生命科学、グループ討論、発表
14. 生き物の匠をまねる
生きものの臓器・組織は人類が利用している工業材料とは全く異なる性質を持っています。酸素や栄養などの物質を透過できる、内部で化学反応が可能、変形できる、表面摩擦が低いなど、水を含んで柔らかい組織特有の性質を示します。このような物質状態をゲルと呼びます。なぜ生きものはゲルで構成されているのか、生体組織がゲルであることの必然性をゲルの機能性の理解を通して学びます。
キーワード : ゲル、生体組織、粘弾性、レオロジー
15. テーマディスカッション⑦
第14回講義担当者
1学期開講の講義中 第14回講義を総括し、総合討論を行います。これまで学んできた講義において、生命科学が様々な学問分野の融合であることを理解し、視野を広げられたことで、将来どのような科学・技術に応用可能であるかを教員と学生、学生と学生で確認、討論します。
キーワード : 生命科学、グループ討論、発表
講義内容詳細 第2学期
1. ガイダンス
大学1年生(文系・理系)が初めて学ぶ科学・技術の世界の中で、「生命科学」分野の授業です。初回は履修ガイダンス。授業担当の学科について紹介を行います。また、授業の進め方(最前線訪問の方法など)、成績評価レポートについても説明します。
キーワード : ガイダンス
2. 自然が選んだ剛と柔の融合
生物は、骨や歯、貝殻のような硬い組織「バイオミネラル」を常温・常圧環境で合成しています。これらはミネラルと高分子が高度に融合した天然の複合材料です。今日、人類はこの生物のものづくりを模倣し、人工的に合成して優れた機能性材料を生み出しています。本講義では、生物がバイオミネラルを作る仕組みを学び、それがどのように合成系で作られ、どのように応用されているかを紹介します。
キーワード : バイオミネラル、骨、硬組織、ソフトマテリアル、電子顕微鏡
3. ふかふかベッドで健やかな細胞
細胞は人間と同じように周りの「硬さ」を感じることができます。人間が眠るときにゴツゴツした硬い地面よりもふかふかなベッドを好むように、細胞にもお好みの「硬さ」があり、その硬さの環境があってはじめて細胞は正常な働きを行います。そのため、周囲の環境が細胞にとって好ましくない硬さになると、細胞は異常な挙動を起こしてしまいます。その一つの例が、がんです。本講義では細胞が「硬さ」を感じる仕組みと、それによって起こる生体内の現象を学びます。
キーワード : 細胞生物学、生物物理学、医工学、メカノバイオロジー
4. 凍結と戦う生命
冬の北海道などの低温環境に生息する生物はなぜ凍らないのでしょうか?あるいは、なぜ凍結しても大丈夫なのでしょうか?これらの低温耐性生物は、その生体内に氷の成長を抑制する様々な物質を蓄えています。その中でも不凍タンパク質と呼ばれる物質は、氷の成長を劇的に抑制します。本講義では、これら物質がどのように氷の成長を抑えているのか?・どのように進化してきたか?・どのように応用できるか?を学びます。
キーワード : 生命科学、低温生物学、タンパク質、構造生物学、凍結保存
5. 最前線訪問①
第2, 3, 4回講義担当者
2学期開講の講義中 第2, 3, 4回の講義から、興味を持ったテーマ一つを選択し研究現場の見学を交えながらより詳細な研究紹介や質疑応答(ディスカッション)を行います。本講義では3テーマの講義ごとに現場訪問を行い、座学の知識がどのように生まれ、どのように今後発展するかを繰り返し学びます。生命科学が様々な学問分野の融合であることを理解し、視野を広げられたことで、将来どのような科学・技術に応用可能であるか実例を介して学びます。
キーワード : 生命科学、最前線、未来
6. 光生物学への招待
生物は、自然環境を生き抜くために、光を利用するための分子機械(光受容蛋白質)を用いています。この蛋白質の基礎研究は、最近になって、“細胞活動を光で制御する分野”「光遺伝学」を産み出しました。この講義では、まず、光受容蛋白質に注目しながら、生物と光の係わりを概観し、次に、光受容蛋白質の中で何が起こっているのかを紹介します。また、新しい分野である「光遺伝学」が、私達に何をもたらすのかについても考えます。
キーワード : タンパク質、光生物、光遺伝学
7. 腸から考える免疫のしくみ
腸は、食べ物を消化し、体に必要な栄養を取り込む生命維持に不可欠な臓器です。腸内には食べ物や微生物など、多くの異物が存在するため、全身で最も発達した免疫システムが備わっています。腸の表面は、一層の細胞からなる上皮組織よって体内と隔てられており、このわずか約1/50 mmの薄い上皮細胞の層を通して体に必要なものと有害なものが選別されています。本講義では、この選別のしくみを手がかりに、生命がどのようにして自らを守っているのかという「免疫」のしくみについて学んでいきます。
キーワード : 腸、免疫、上皮細胞、異物認識
8. 進化を予測する
生物の進化は偶然の積み重ねなのか、それとも予測可能な法則に従っているのか?ダーウィン以来の問いに、現代も多くの研究者が挑んでいます。本講義では、ヒトの環境改変の影響を受けた野外生物の60年間にわたる変化や、ウイルスの薬剤耐性進化など具体例を通じて、進化を「予測する科学」として捉える視点を紹介します。数学やコンピュータによる計算が生命科学とどのように融合し、未来予測を可能にしつつあるのかを学びます。
キーワード : 数理生物学、進化、シミュレーション
9. 最前線訪問②
第6, 7, 8回講義担当者
2学期開講の講義中 第6, 7, 8回の講義から、興味を持ったテーマ一つを選択し研究現場の見学を交えながらより詳細な研究紹介や質疑応答(ディスカッション)を行います。本講義では3テーマの講義ごとに現場訪問を行い、座学の知識がどのように生まれ、どのように今後発展するかを繰り返し学びます。生命科学が様々な学問分野の融合であることを理解し、視野を広げられたことで、将来どのような科学・技術に応用可能であるか実例を介して学びます。
キーワード : 生命科学、最前線、未来
10. やわらかくて、強くて、運べる ― ゲルの基礎と設計指針
ゲルは大量の溶媒を含んでいながらも固体的にふるまう物質です。溶媒としての機能を示しながらも強度を保てることから、これまでに様々な用途で使うことができるゲルが開発されてきました。ゲルの研究は日本が強く、特に北海道大学では世界トップレベルのゲル研究が行われています。本講義では、ゲルの基礎的な知識、硬さや強度を制御するための設計指針、物質輸送材料としての応用などについて、最新の研究成果を交えながら紹介します。
キーワード : ゲル、力学特性、物質輸送
11. 生命を形作る高分子の科学
私たちの身体は、車や飛行機のような硬い物質でできたものとは異なり、全体として柔らかい構造を持っています。この柔らかさは、私たちの生体組織を形作っている高分子の性質に由来しています。本講義では、分子がひも状に長くつながった高分子の基礎的な科学を学び、それらが生命の中でどのように働いているかを、高分子の物性や構造や機能の観点から考えていきます。
キーワード : 高分子、物性物理、構造解析
12. 植物免疫研究〜大発見のその時〜
「農作物を病害から守ること」は、人類が直面してきた普遍的課題です。私たちは、植物がどのように多様な病原体を認識し、免疫応答を活性化させるのかについて研究してきました。本講義では、これまでの植物免疫を対象とした研究生活の中で、いつ・どのようにして「発見」に出会うことができたのかを紹介します。また、大学を卒業し、海外の最先端の研究所に留学した際の思い出話を含めた体験談も紹介します。
キーワード : 植物科学、免疫、海外留学
13. 最前線訪問③
第10, 11, 12回講義担当者
2学期開講の講義中 第10, 11, 12回の講義から、興味を持ったテーマ一つを選択し研究現場の見学を交えながらより詳細な研究紹介や質疑応答(ディスカッション)を行います。本講義では3テーマの講義ごとに現場訪問を行い、座学の知識がどのように生まれ、どのように今後発展するかを繰り返し学びます。生命科学が様々な学問分野の融合であることを理解し、視野を広げられたことで、将来どのような科学・技術に応用可能であるか実例を介して学びます。
キーワード : 生命科学、最前線、未来
14. 糖と生命
光合成による糖の合成とその利用は生物界の根源的なエネルギーと物質の循環システムである。その利用において糖はエネルギー源や細胞壁等の構造材料にとどまらず、様々なシグナル分子としても生命活動を彩っている。本講義では細胞表面の多彩な糖の仲間(糖質)に焦点を当て、多細胞生物の成り立ちや共生、感染など、シグナルとしての糖質の機能とその機能を探求する上での問題点について紹介します。
キーワード : 糖質、エネルギー、シグナル分子、生命社会、感染・免疫、創薬
15. 総合ディスカッション
第14回講義担当者
グループディスカッションを行います。第14回講義を題材にまずテーマディスカッションを行い、続いて2学期開講の講義全体を振り返り生命科学とは何かを過去、現在、未来をテーマにディスカッションします。コロナ等の状況に応じて内容を変更することがあります。
キーワード : 生命科学、最前線、未来